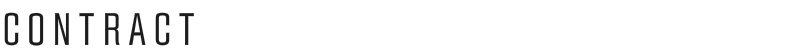
![]()
本契約書式は、具体的な事案を前提に作成した物で、当事者等の具体的な事項については伏せ字とした物です。しかし、契約作成の前提となる契約に至る経緯、相手方の性格、買い急ぎ売り急ぎ等の契約の立場等、契約を取り巻く細部の状況についての説明はしておりません。
「契約書作成のポイント」でもご説明しているように、契約上の条件や状況によって、当事者の義務と権利は大きく変わってきます。
弊会は、契約書式を使用する方に費用負担を求めない(無償)と共に、本契約書式を使用して作成した契約書の運用結果についてもいかなる責任も負いません。本契約書式の使用は、必ずご自身の責任と判断で行ってください。
また、契約書の作成等にかかわる無料相談は行っていません。
ご相談をご希望される際は、有料となります。ご相談の際は「お問い合わせ/連絡用フォーム」 からお申し込みください。
からお申し込みください。
以上の注意事項をご承諾いただいた上で契約書式をご利用ください。これらの注意事項をお読みにならずお問い合わせいただいても、当会は対処いたしませんので、あらかじめご承知おきください。
文章中で、法律条文を多々引用しておりますが、特に法律名を表記していない引用条文はすべて民法です。
![]()
契約当事者の意思表示の内容が、一致している状態としての合意が存在することによって契約は成立します。
契約は、二人以上の人によって互いに権利義務を発生させる法的拘束力を持った約束をすることです。
その合意によって成立する契約を諾成契約といい、合意に加え目的物の引渡があって成立する契約を要物契約といいいます。
保証契約(446条2項)のように、契約書を作成し締結しないと成立しない契約もありますが、契約書を作成していなくても、「合意」が成立することで契約は法的には成立しています。
民法の第2章では「契約」の規定がされていますが、その規定中に、典型契約として、贈与をはじめとして売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解まで合計13種類の契約の型を定められています。
典型契約のうち要物契約とされているのは消費貸借(587条)、使用貸借(593条)、寄託(657条)契約で、それ以外の契約は諾成契約です。
![]()
契約の内容をどうするか、誰と契約をするか、契約を結ぶか結ばないかに自由かや形式をどうするか、契約を結ぶか結ばないかは当事者の自由です。
とはいえ、契約内容を始め自由に決められない場合があります。
いや、現代の経済生活の中では内容を自由に決められない契約が大半です。
銀行取引、宿泊、携帯電話等々、契約の相手はその契約をするかしないかの選択する自由しか残っていないのが現実でしょう。
法律には直接規定されていないのですが、近代資本主義の初期に特に強調された大原則です。しかし、歳月の経過と共に、その自由に制限が付けられてきています。
<1> 契約内容の自由については、例えば借地借家法の規定に反する賃借人に不利な特約は、借地借家法9条・16条・21条・30条・37条により、しなかったもの(無効)とみなされてしまいます。
<2> 法律上、書式化が要求されている場合は少ないです。しかし、書面に書かれない贈与はいつでも撤回される(550条)、農地の賃貸借契約は書面化が義務付けられています(農地法21条)。
また、消費者保護・弱者保護の立場から、宅地建物取引業法の規定には契約の書面化が随所に規定されています。
<3> 結ぶか結ばないかの締結の自由も、独占的な企業や公共的な事業(郵便・鉄道・ガス・水道・医師・公証人など)や、社会政策的な場面(借地借家法13条・14条・33条などの建物や造作の買取請求権の行使としての売買)では締結が強制されています。
<4> 契約相手にだれを選ぶかという相手方選択の自由も、締結の自由が奪われている場合には相手方選択の自由も制限されています。
![]()
売買契約等諾成契約は、相手方との合意があれば契約は成立します。要物契約にしても、物の引渡(金銭消費貸借契約では、貸主から借主への貸金の引渡)があれば契約は成立です。
しかし、人は忘却の動物です。意識してか無意識でかはともかく、一方が契約内容を忘れてしまったら、忘れないまでも時間の経過と共にあやふやになってしまうことは容易に想像できることです。
いわゆる口約束では、貸した金を返してくれと訴えてみても、借りたはずの相手方が金銭の受領を認めなかったら、金銭の受領を認めても『あの金はもらったモノじゃないか』と、金銭消費貸借ではなく贈与を主張されたら、返してもらうのは相当困難なこととなってしまいます。
もちろん、やったモノと覚悟してお金を貸したのでしたら口約束でいいのかもしれませんが、それでも、借りた方からしたら、いつまでに返すのか等の返済条件を残しておかないと、せっかくお金を返しても、貸した側と条件について食い違いが生まれてしまうことも考えられます。
ともかく、大半の契約は、親子、夫婦、兄弟姉妹のような血縁であったり顔見知りの人と行うことはないのですから、契約内容を書面にしておく必要があります。
そうやって契約書を作成することにより、契約内容が明示、確定され、後日争いが生じそうになっても契約内容を見返すことができますし、仮に争いが生じてしまっても、正しい契約書が証拠となります。
また、「賃料を2ヶ月以上支払われなかった場合は、賃貸借契約は解除される」等の条項を付けることによって、想定されるトラブルに対し事前に手を打っておくことができますし。
また場合によっては、相手が契約した内容を守らなかった時に、契約書を示して、契約を守るように暗に強制する効果もあります。
![]()
契約相手の確認をしないことで、後で契約が無効になったり取消されたりしてしまうことがありますので、契約する前にまず契約相手の確認をします。
相手が個人の場合は、運転免許等の公的機関の発行する顔写真付き証明証で本人確認します。その際、20歳未満だった場合、親権者(後見人)の同意がないと後で契約が取り消されることがありますので、親権者の同意をとっておく必要があります。
また、相手が高齢者だった場合や、弁識能力、判断能力に通常とは異なる物を感じた時は、相手方に市区町村の発行する「身分証明書」と「登記されていないことの証明書」を用意してもらい、任意後見、補助、補佐、後見の登記のされていないことを確認しておいた方が安心できます。
仮にそれぞれの登記がされていた場合は、その「登記事項証明書」にのっとりその代理権限や同意の内容や範囲を確認する必要があります。
![]()
相手が株式会社等の営利社団法人の場合は、契約の内容によりますが、原則としては法人の代表権者、株式会社であれば代表取締役が契約の当事者となりますから、法人の登記簿謄本を確認します。法人の所在地、目的、資本金の額、役員の氏名、代表者の氏名と住所等が記載されています。
登記内容は変更される可能性がありますので、できるだけ直近のものを取り寄せるようにします。変更登記時期が法定されている法人の場合は、その変更登記時期には注意が必要です。
また、不動産登記での仮登記のように、代表取締役の権利を制限するような仮登記がされていた場合、その代表取締役を契約相手としても、後日無効とされる場合がありますので、仮登記が抹消され相手の復権を信じるべき根拠がないのでしたら、契約相手としては避けた方がいいでしょう。
相手が営利社団法人以外の法人の場合、会社と同じように、登記簿そして定款、寄付行為を確認します。
また重要な資産の処分や借入につては、学校法人の場合は評議委員会の議決が必要であり、宗教法人の場合は責任役員会の議決をうけた上で信者らに広告する必要があります。
この点は、株式会社についてもいえることで、重要な資産処分の場合は、後日のトラブルを避けるためにも取締役会の議決を受けておいた(議事録を提出してもらった)方がいいでしょう。
学校法人、宗教法人と契約する場合は、その契約内容に基づき学校法人法等の根拠法を確認してください。
登記されていない町会や同好会等の団体や「山田工務店 代表 山田太郎」のような個人企業の場合は、個人として扱います。
![]()
建物の場合余り問題にならないが、土地の売買、賃貸等の契約をする場合、境界等で対象物件の特定をしないでいると、地積を確定することもできないので、対象土地の範囲を特定する必要があります。公図に書かれていても実際の土地(地積)が存在しないこともあるので、注意が必要です。
特に賃貸借(借地)契約の場合は、大きな土地を分筆することなく賃貸することが多いので、境界を明示して賃貸借契約しないと、後日どこを借りたのかはっきりしなくなる恐れがあります。
![]()
印紙税は印紙税法の別表1の課税物件表に掲げられている国内で作成された文書に課税されます。
2部作成したら、それぞれに課税されます。
1部を作成し、相手方はそのコピーを持つというような場合、コピーしたままの文書は課税文書とはならないので、課税は1部だけにされます。
ただ、コピーした文書に当事者が契約の証明をした場合、課税文書に該当しますので注意が必要です。
課税対象は限定的ですので、課税物件表に掲げられていない文書は課税物件となりません。
ですから、1号文書に2として(地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書)が掲げられていますが、それ以外の賃借権設定の契約書にはふれていませんので、建物の賃貸借契約書は課税物件でないので印紙税を納める必要はありません。
ただし、契約書の表題で課税文書か非課税文書かを判断するのではなく、内容で判断しますので、建物賃貸借契約と書かれていても、文書の中で敷金を受領した等の受領文言が入っている場合は17号文書(領収書等の受取書)にあたり、その規定に従って印紙を貼付しなくてはなりません。
また、事務所等の賃貸借契約に建築協力金、保証金等の契約途中で一定の返還する金員を預かることがありますが、その返還条件を賃貸借契約の中に規定すると、1号文書3の(消費貸借に関する契約書)にあたり、そこ規定の従って印紙を貼付しなくてはなりません。
別表1には非課税文書についても規定されています
1号文書(不動産等の譲渡等に関する契約書等)並びに2号文書(請負に関する契約書)では、契約金額1万円未満、3号文書(約束手形・為替手形)では10万円未満、17号文書(受取書)では3万未満を非課税文書としています。
また、17号文書(受取書)については、営業に関しない受取書を非課税文書としています。
これは、個人が自宅を売った時の代金の領収書には印紙を貼付する必要がない、ということの根拠です。個人といっても、建物を貸すとなると営業行為ですから、個人が自宅を賃貸した時の家賃の受取書が3万円を超えていた場合は課税文書となり印紙貼付しなくてはなりません。
不動産関係の契約書で日常関係がないと思われますが、印紙税法の別表2には国、地方公共団体以外の非課税法人の表が、また別表3には非課税文書の表が掲げられています。非課税法人かどうかは契約の相手方が把握していることですし、非課税文書についても、文書作成者が特定されていますし、不動産関係にはほとんど関係のない文書ばかりですから、別表2ないし3を気にかける必要はほとんどないうようです。
![]()
印紙税の納税義務者は課税文書の作成者です。
売買契約で売り主、買い主がいるように、二人以上で作成された文書は連帯して納税する義務があります。
単独で作成する受取書(領収書)は、受領書を受け取った人には納税義務はありません。
印紙税法は、国内法ですから、日本国内で作成された文書について納税義務が発生するので、日本以外で作成された文書は課税文書とはされません。日本国籍の者同士が日本に所在する不動産の売買契約書を、双方の別荘のあるオーストラリアのパースで作成した場合は、その文書は課税対象外文書となりますので、印紙を貼付する必要がありません。
その場合は、文書作成場所を文書(売買契約書)中に記載しておく必要があります。
これは、課税場所だけがポイントですので、日本国籍以外の者同士が日本国内で課税文書を作成した場合は法に基づき課税されます。
印紙税の納付は、課税文書に作成の時までに貼付して、文書と印紙の文様にかけて(割り印または署名によって)消印することで納付したことになります。印紙貼付の他にも、税印(印法9条)「押印サンプル」、印紙税納付計器(印法10条)「印刷サンプル」等によっても納税できますが、契約書作成の場合、印紙貼付以外の方法を想定する必要はないと思います。
印紙税を納付しなかった場合はどうなるのかといいますと、第一に過怠金が課せられ印紙税とは別に過怠税が徴収されます。その場合の過怠金は印紙税の倍額です(印法20条1項)。印紙が貼付されているが消印されていない場合は過怠金は印紙税と同額(全く貼っていなかった場合の半額)となります(印法20条3項)。
また、調査を受けることを知らなかった上で自主的に税務署に申し出て納付した場合は印紙税額の10%(印法20条2項)となりますが、課税文書が手元にあるにもかかわらず税務署に通知をして納付する状況は不動産取引に関しては余り想定できないです。
納付しなかった場合、過怠金の他に罰則(印法22条1~2項)が課されます。1年以下の懲役、20万以下の罰金ですが、印紙税額の3倍が20万円を超えている時は当該印紙税額の3倍以下の罰金となります。
ということで、印紙税の不納付は、最大印紙税額の5倍の額を余計に支払い、懲役3年のおまけまでついてくるかもしれないリスクのあることを覚悟しておきましょう。
![]()
一つの文書に複数の課税物件がある場合の印紙税額は、法人税法別表1の「課税物件表の適用に関する通則」に、1号または2号文書と2号から17号文書がある場合は原則として1号または2号文書が優先する等々細かく規定されています。
たとえば、売買代金1,000万円の土地売買契約書(1号文書)中に売買代金全額(1,000万円)の受領文言(17号文書)が記載されていても、1号文書として扱い、印紙税の計算も売買代金1,000万円に対する1万5千円(平成23年3月31日まで本則2万円が軽減されています)だけでよく、17号文書に必要な4千円の印紙税は必要ありません(通則3-イ前段)。
課税物件の組み合わせも種々想定されますので、作成文書に複数課税物件がある場合は、法人税法別表1の「課税物件表の適用に関する通則」で、作成文書がどの事例に該当するかを確認する必要があります。
複数の課税の場合は、具体的事例を使った国税庁の「解説書」の方が分かりやすいようです。
印紙税法ではひっきりなしに出てくる課税価格の階層ですが、「以上」「以下」はその数値を含み、「未満」「超える」はその数値を含みません。
たとえば、10万円以下(以上)は10万円を含みますが、10万円未満(超える)は10万円を含みません。
![]()
押印。
1.消印
消印は契約書に貼付された印紙の納税方法で、印紙税法第八条(印紙による納付等)第2項に「課税文書の作成者は、前項の規定により当該課税文書に印紙をはり付ける場合には、政令で定めるところにより、当該課税文書と印紙の彩紋とにかけ、判明に印紙を消さなければならない」規定されておりますので、契約書と印紙にかけてはっきりと押印します。
契約者全員の印鑑で押す必要もなく、契約に使った印鑑かである必要もありませんが、当事者が二人程度であれば、双方がそれぞれの契約書に契約印で消印するのが通常です。
2.割印・契印
契印は、契約文書が二枚以上にわたった場合そのつなぎ目に押印するものです。
契約書が数枚にわたる場合はそれぞれのつなぎ目に押印する必要があるため、契約書用の製本テープを使い、割印は一箇所で済まします。
契印については、民法施工法第六条第2項に「証書カ数紙ヨリ成レル場合ニ於テハ前項ニ掲ケタル印章ヲ以テ毎紙ノ綴目又ハ継目ニ契印ヲ為スコトヲ要ス」と規定されています。
割印は、民法施工法第六条第1項に「私署証書ニ確定日附ヲ附スルコトヲ登記所又ハ公証人役場ニ請求スル者アルトキハ登記官又ハ公証人ハ確定日附簿ニ署名者ノ氏名又ハ其一人ノ氏名ニ外何名ト附記シタルモノ及ヒ件名ヲ記載シ其証書ニ登簿番号ヲ記入シ帳簿及ヒ証書ニ日附アル印章ヲ押捺シ且其印章ヲ以テ帳簿ト証書トニ割印ヲ為スコトヲ要ス」と規定され、契約書においても、契約書が二通以上にわたった時に、その文書の同一性を証するために印影が双方に渡るように押すことです。
ただし、公証人法第五十九条に「認証ヲ与フヘキ証書ニハ登簿番号、認証ノ年月日及其ノ場所ヲ記載シ公証人及立会人之ニ署名捺印シ且公証人其ノ証書ト認証簿トニ契印ヲ為スコトヲ要ス此場合ニ於テ嘱託人ノ申立アルトキハ第三十六条第四号及第六号乃至第八号ニ掲グル事項ヲ記載スルコトヲ要ス」とあるように、契印と割印が区別なく使用されているように、契印と割印を区別することなく使っている場合も多々あります。
3.署名(記名)押印
契約書に署名(記名)押印する場合は、署名(記名)の最後の文字にちょっとかかるように押印します。
![]()
契約文書の訂正
1.訂正印
訂正印は契約文書の文字を間違えたときに押印するものです。
文字訂正の仕方は、たとえば2文字削除して3文字追加する場合は「削除2字加入3字」と記入し契約当事者が文字の上に訂正印を押します。
訂正文字数が同じ場合は「訂正1字」と記入し、それぞれ訂正印を押します。
文字訂正(削除と加入)の仕方例。
2.押印の訂正
印鑑を間違えたとか、押印に失敗した場合の押印の訂正方法は、間違えた印鑑を逆さまにして上からもう一度押印し印影をつぶしてしまい、改めて空白部分に押印します。
3.完成された契約書の訂正
すでに完成された契約書で、不動文字があり空欄がある時は、以下のように訂正します。
・手付金と残代金での決済の場合で内金の支払いがない場合
内金(第3条) 第1回 平成-年-月-日 ──────── 円
第2回 平成-年-月-日 ──────── 円
・契約文全体がいらない場合は斜線で訂正する。
・契約分の最後に大きな余白ができてしまった場合は、「以下余白」または「以上」と記しておく。
![]()
特別法である宅地建物取引業法(以下業法という)の契約書条項への影響。
宅地建物取引業者(以下業者という)が売り主であったり、売買の代理又は媒介により契約する場合、並びに業者が賃貸借の代理または媒介により契約する場合は、業法第37条により記載必須事項が定められています。
また、損害賠償額(第38条)並びに、手付金額(第39条)の規定は、売買契約における強行規定ですので、買い主に不利となるものは無効です。
第37条違反(記載漏れ)に対しては、50万円以下の罰金(業法第83条第1項第2号)という罰則規定がついています。
業法第37条に該当する契約の場合、契約書面の交付に先だって、重要事項説明がされますので、重要事項説明書に記載された事項と契約書面の事項との整合性を確認してみます。
第37条(書面の交付)
宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買又は交換に関し、自ら当事者として契約を締結したときはその相手方に、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 当事者の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示又は当該建物の所在、種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示
三 代金又は交換差金の額並びにその支払の時期及び方法
四 宅地又は建物の引渡しの時期
五 移転登記の申請の時期
六 代金及び交換差金以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
七 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
九 代金又は交換差金についての金銭の貸借のあつせんに関する定めがある場合においては、当該あつせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置
十 天災その他不可抗力による損害の負担に関する定めがあるときは、その内容
十一 当該宅地若しくは建物の瑕疵を担保すべき責任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 当該宅地又は建物に係る租税その他の公課の負担に関する定めがあるときは、その内容
2 宅地建物取引業者は、宅地又は建物の貸借に関し、当事者を代理して契約を締結したときはその相手方及び代理を依頼した者に、その媒介により契約が成立したときは当該契約の各当事者に、次に掲げる事項を記載した書面を交付しなければならない。
一 前項第一号、第二号、第四号、第七号、第八号及び第十号に掲げる事項
二 借賃の額並びにその支払の時期及び方法
三 借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額並びに当該金銭の授受の時期及び目的
3 宅地建物取引業者は、前二項の規定により交付すべき書面を作成したときは、取引主任者をして、当該書面に記名押印させなければならない。
第38条(損害賠償額の予定等の制限)
宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。
2 前項の規定に反する特約は、代金の額の十分の二をこえる部分について、無効とする。
第39条(手附の額の制限等)
宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいかなる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 前項の規定に反する特約で、買主に不利なものは、無効とする
条文のリーダー下線部分には条文説明へのリンクがついています。
土地売買契約書
売主 ●●●●●(以下「甲」という)と、買主 ●●●●(以下「乙」という)とは、甲所有の不動産の売買に関し、以下のとおり契約する。
第1条(目的)
甲は、その所有する下記不動産(以下「本件土地」という)を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。
<不動産の表示>
所在地 ●●●●●●●●●
地 番 ●●●●番地●●
地 目 宅地
地 積 ●●●.●●平方メートル
第2条(売買代金)
本件土地の売買代金は、金●●●●万円也(税別)とする。
第3条(支払方法)
乙は、甲に対し、前条に定める売買代金を次のとおり支払う。
(1)本契約締結と同時に手付金として、金●●●万円也(税別)
(2)甲による所有権移転登記完了と同時に、金●●●万円也(税別)
(3)本件土地の引渡しと引き換えに、金●●●万円也(税別)
第4条(地積測量と売買代金の精算)
甲は●●●●年●月●日までに境界を明示し、実測により確定した地積測量図を乙に交付する。
2 測量の結果、不動産の表示に記載された本件土地の地積に増減が生じた場合は、1平方メートル当たり●●万円により売買代金の精算をする。
第5条(登記手続き)
所有権移転登記は、第3条2号記載の代金支払いまでに完了させるものとし、甲および乙は、その日までに本件土地の所有権移転登記申請に必要な書類を準備する。
2 所有権移転登記手続きに要する費用は、すべて乙の負担とする。
第6条(費用負担)
前条の所有権移転登記手続きに要する費用の他、収入印紙等本契約に要する費用は甲乙折半で負担する。
2 本件土地にかかる公租公課等の負担は、所有権移転登記の日をもって区分し、その前日分までは甲が、その日以後の分は乙が、それぞれ負担する。
第7条(引渡し)
本件土地の引渡しは、●●●●年●月●日に現地で甲乙立ち会いのもと、第3条3項の支払いと引き換えに行うものとする。
第8条(危険負担)
本件土地が、前条の引渡完了前に天災地変その他甲の責めに帰すことのできない理由により、滅失または毀損し乙が買い受けの目的を達することができなくなった場合は、次の各号の定めによる。
(1)滅失の場合は、甲はすでに受領済みの金員の全額を乙に返還し、本契約は解除される。
(2)毀損の場合は、甲は自己の負担で現況に回復し、乙に引き渡すものとする。ただし、毀損の程度により甲の選択により、契約を解除することができる。
2 前項の場合、乙は甲に対し損害賠償の請求をすることはできない。
第9条(瑕疵担保責任)
本件土地にかくれたる瑕疵を発見し、またこれにより乙が損害を受けた時は、甲は担保の責めを負わなくてはならない。
2 前項の瑕疵担保責任の期間は、本件引渡しの日より2年間とする。
第10条(保証)
甲は、本件土地について、抵当権、根抵当権その他乙の完全な所有権の行使を妨げる一切の権利の存在しないことを乙に対し、保証する。
2 万が一、本件土地の乙の所有権の行使に妨げとなる事由の生じたときは、甲の責任において解決し、乙には法律上の一切の迷惑をかけないことを約する。
第11条(契約解除)
甲または乙がこの契約に定める各条項に違反したときは、他方の当事者は、相手方に何らの事前催告なくして、この契約を解除することができる。
2 甲は、前項の場合には、第3条にもとづき、すでに乙より受領済みの手付金について、これを違約金として収納することができる。
3 乙は、第1項の場合には、第3条にもとづき、すでに支払った手付金の返還を受けると同時に、甲に対し、手付金と同額の違約金を請求することができる。
第12条(損害賠償)
甲又は乙が相手方の契約不履行によって損害を受けた時は、前条の違約金とは別にその損害賠償金を相手方に請求することができる。
第13条(誠実な協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
第14条(合意管轄)
本契約に関して紛争が生じた場合には、甲の住所地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各署名押印のうえ、各1通を保有する。
●●●●年●月●●日
(署名押印)
甲(住 所) ●●●●●●●●●●●●●●
(氏 名) ●●●●● 印
乙(住 所) ●●●●●●●●●●●●
(氏 名) ●●●● 印
条文のリーダー下線部分には条文説明へのリンクがついています。
建物賃貸借契約書
賃貸人 株式会社●●●●(以下、「甲」という)と、賃借人 ●●●●(以下、「乙」という)と連帯保証人●●●●とは、以下のとおり建物賃貸借契約を締結した。
第1条(契約の目的)
甲は、その所有に係る下記表示の建物(以下本件建物という)を乙に賃貸し、乙はこれを乙の居室として使用する目的をもって賃借する。
物件の表示
<所 在> 東京都●●区●●●丁目●●番地●
<家屋番号> ●●番●の● <種類> 共同住宅
<構 造> 鉄筋コンクリ-ト造陸屋根●階建の内●階●●●号室
<床 面 積> ●●.●●平方メートル
第2条(賃貸借の期間およびその更新)
賃貸借期間は、●●●●年●月●日から●●●●年●月●日までとし、乙は新賃料の●ヶ月分の更新料を支払って契約の更新をすることができる。
2 期間満了の●ヶ月前までの間に当事者から書面による更新を拒絶する旨の意思表示がない時は、従前の契約と同一の条件で契約が更新されたものとする。
3 更新後の契約期間は、満●年間とする。
第3条(賃料)
毎月初より月末迄を一ヶ月とする賃料は、月額金●●●,●●●円也と定め毎月●日までにその翌月分を、乙は甲に持参もしくは乙の預金口座より甲又は甲の指定した預金口座に振り替えることによって支払うものとする。
第4条(共益費)
乙は甲に対し、前条の賃料のほかに、共益費として月額金●,●●●円を賃料と共に支払うものとする。
2 共益費は敷地内並びに建物共用部分の維持管理に必要な水道光熱費、電灯等の交換費、清掃費に充てるものとする。
第5条(諸費用の実費負担)
乙は、本件建物で使用する電気、ガス、水道等の本件建物専用にかかる各種費用を支払うものとする。
第6条(敷金)
乙は、敷金として賃料の●ヶ月相当額を甲に差入れるものとする。この金員には利子を付せず、本契約が終了又は解除により返還する。乙に延滞賃料又は損害賠償金がある時はその合計額を差し引いた残高を、本件建物の明渡しの日より●ヶ月以内に返還する。
第7条(敷金の充当)
乙は賃料の支払を怠ったとき又は損害賠償金を支払わなかったときは、甲は敷金をもってその弁済に充当することができる。但し、乙において敷金をもって乙の債務の弁済に充当することを要求できない。
第8条(乙の管理義務)
乙は、本件建物および共用部分その他付随して使用できる部分を、善良なる管理者の注意をもって占有または使用し、かつ別に定める管理規約その他の指示を遵守しなければならない。
2 本件建物の修繕は、乙による人為的破損および日常の小修理に属するものについては、乙が負担して行なうものとする。
第9条(現状回復・損害賠償義務)
乙の責めに帰すべき事由により本物件を汚損・毀損もしくは滅失したとき、または甲の承諾なしに本物件の現状を変更した時は、乙は速やかにこれらを原状に復し、又は損害を賠償する。
第10条(禁止又は要承諾行為)
乙は本件建物の使用にあたり下記に掲げる行為を行なってはならない。
(1)本件建物の全部もしくは一部を転貸すること。
(2)銃砲、刀剣類又は爆発性、発火性を有する危険な物品等を保管すること
(3)大型の金庫その他重量の大きな物品を物品等を搬入し備え付けること
(4)排水管を腐蝕させるおそれのある液体を流すこと
(5)大音量でテレビ、ラジオ等の操作をし、又はピアノ等の演奏を行なうこと
(6)鑑賞用の小鳥、魚等の明らかに近隣に迷惑をかけるおそれのないもの以外の動物 を飼育すること
2 乙は甲の書面による承諾を得ずして本件建物の使用にあたり下記に掲げる行為を行なってはならない。
(1)本件建物の改造もしくは模様替をすること
(2)廊下、階段等の共用部分に物品を置くこと
(3)同居者を変更すること
(4)乙及び居住者以外の名義を表示すること
第11条(甲の立入)
甲、甲の使用人もしくは甲の指定した者は、防火、保全その他本建物管理上必要ある時はあらかじめ乙の同意を得て、又火災による延焼を防ぐ等の緊急の必要ある時はあらかじめ乙の同意を得ることなく室内に立ち入り必要な処置をすることができる。
2 乙は、正当な理由なく前項の規定に基づく甲、甲の使用人もしくは甲の指定した者の立入を拒否することはできない。
3 本賃貸借契約終了後において本件建物を賃借しようとする者又は譲り受けようとする者が下見しようとする時は、甲、甲の使用人並びに下見をしようとする者は、あらかじめ乙の同意を得て、本件建物に立ち入ることができる。
第12条(解約予告)
乙が本契約を解約する場合は、甲に対しその●ヶ月前迄に書面による通知をしなくてはならない。但し、賃料の●ヶ月分相当額の金員の支払いをもって即日解約することができる。
第13条(契約の解除)
甲は乙が次の掲げる義務に違反した場合において、甲が相当の期間を定め当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されない時は、本契約を解除することができる。
(1)第3条並びに第4条に規定する賃料等支払義務
(2)第5条に規定する諸費用の実費負担義務
2 甲は乙が次の掲げる義務に違反した場合において、当該義務違反により本契約を継続することが困難であると認められるに至った時は、本契約を解除することができる。
(1)第1条に規定する使用目的遵守義務
(2)第10条に規定する遵守義務
(3)その他本契約書に規定する乙の義務
3 甲は乙において本物件を使用するにあたり、次のいずれかの事由が生じた場合において、本契約を解除することができる。
(1)乙又はその同居人の行為が、本物件内の共同生活の秩序を著しく乱すものと認められる場合
(2)乙又はその同居人に覚醒剤、売春など警察の介入を生じさせる行為があった場合
(3)乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものと判明した場合
(4)乙又はその同居人が、暴力団若しくは極左・極右暴力集団の構成員、又はこれらの支配下にあるものを本物件に反復、継続して出入りさせたり、近隣居住者の平穏を害するおそれのある行為があった場合
(5)乙又はその同居人が、本物件を暴力団若しくは極左・極右暴力集団の事務所かアジトとして使用した場合、あるいは、第三者に同様の目的として使用することを許容した場合
第14条(明渡に伴う乙の義務)
本契約が期間の満了、解約、解除その他の事由により終了したときは、乙は次の各号に従い、本件建物を明渡さなければならない。
(1)乙が甲の承諾を得ないで本件建物の現状を変更した場合には、これを原状に復する。但し、乙がこれを行わないときは甲において行い、その費用は乙の負担とする。
(2)乙は甲に対し、移転料その他如何なる名目をもってするも金銭的請求をすることはできない。
(3)乙は甲に対し、本契約終了後明渡完了に至るまで賃料の2倍相当額の使用損害金を支払う。
第15条(甲の免責事由)
甲は、天災、地変、火災、盗難により生じた損害または電気、ガス、水道等の設備の破損等により生じた損害に関しては、甲に重大なる過失のない限り一切その賠償の責を負わないものとする。
第16条(賃借権の消滅)
本物件が、天災地変その他甲または乙の責めによらない理由により全部又は大部分が使用できなくなったとき、または都市計画等により建物が収去されるときは、本契約に基づく賃借権は消滅する。
第17条(消費税の負担)
乙が甲に支払う金員の内、賃料、共益費、礼金、損害金、保証金の償却費等甲に消費税の支払義務の発生する金員には、支払うべき金額に消費税額を加算して支払わなくてはならない。将来消費税の新設、廃止、消費税率の見直し等の変更があれば甲、乙、ともにその規定に従う。
第18条(連帯保証)
連帯保証人は、乙と連帯して、合意更新・法定更新にかかわらず本契約が存続する限り、本契約から生じる乙の一切の債務を負担するものとする。
第19条(誠実な協議)
本契約に定めのない事項、または本契約の各条項の解釈について疑義が生じたときは、甲乙は誠意をもって協議し、これを定めるものとする。
第20条(管轄裁判所)
甲および乙は、本契約について紛争を生じた場合は、甲の住所地の裁判所を第一審の管轄裁判所とすることにあらかじめ合意する。
上記契約の証として本契約書2通を作成し、それぞれ署名押印のうえ、甲、乙各一通を保有する。
●●●●年●月●●日
(署名押印)
住所 ●●●●●●●●●●●●
甲(賃貸人)
氏名 株式会社 ●●●●
代表取締役 ●●●● 印
住所 ●●●●●●●●●●●●●●
乙(賃借人)
氏名 ●●●● 印
住所 ●●●●●●●●●●
連帯保証人
氏名 ●●●●● 印
土地売買契約書及び建物賃貸借契約書以外の契約書式は、会員登録頂くことで無償でご使用になれます。会員登録

契約書式はOpenOfficeの文書ドキュメントで作成しております。
書式を利用する場合はOpenOfficeが必要となります。
お持ちでない方は右のアイコンをクリックしてOpenOffice をダウンロードの上ご利用ください(無償)。
をダウンロードの上ご利用ください(無償)。
また、普段MicrosoftOfficeの文書作成ソフト(Ward)をお使いの方は OpenOffice で文書を読み込んだ後、ご利用のファイル形式に変換してお使いください。
書式の閲覧だけでしたらPDFファイルがご利用になれます。
弊会は、本契約書式を使用して作成した契約書の運用結果についていかなる責任も負いません。
本契約書式の使用は、ご自身の責任と判断で行ってください。
会員登録

OpenOfficeのダウンロード

![]()
101.土地売買契約書(odt 15KB)
101.土地売買契約書(pdf 86KB)
![]()
![]()
201.建物賃貸借契約書(odt 17 KB)
201.建物賃貸借契約書(156 KB)
![]()
HOME > 契約書
不動産コンサルタント会議 since 2010-04-27 / Copyright 2010 Real Estate Consultants,The Meeting of Japan. All Rights Reserved.
